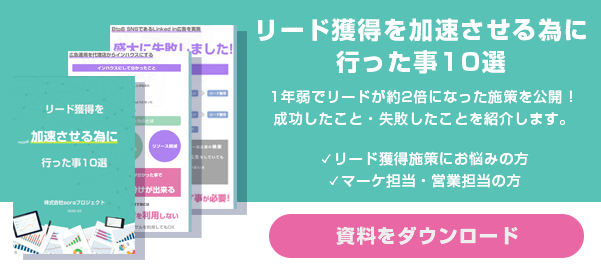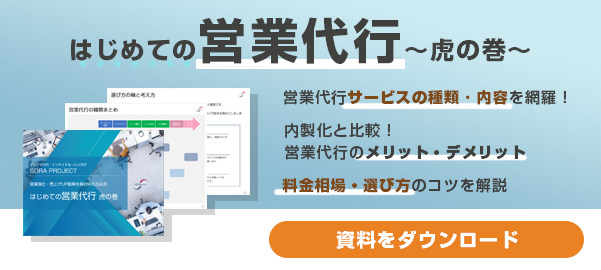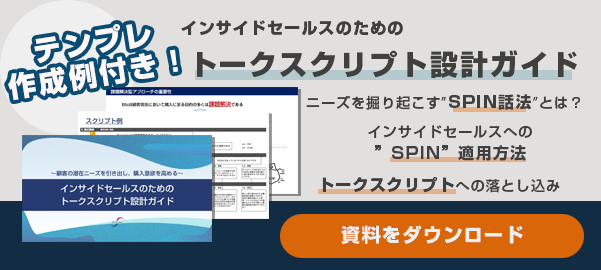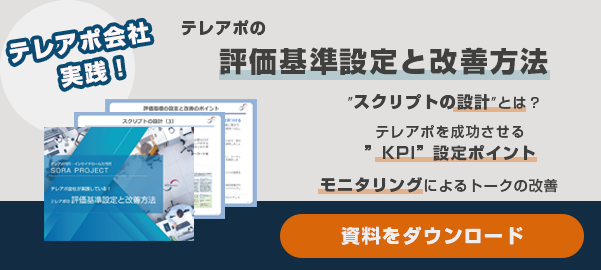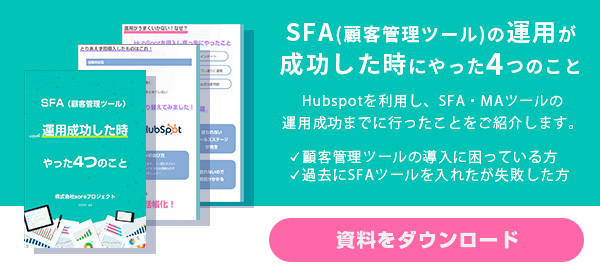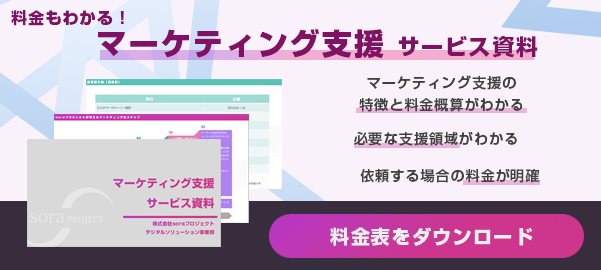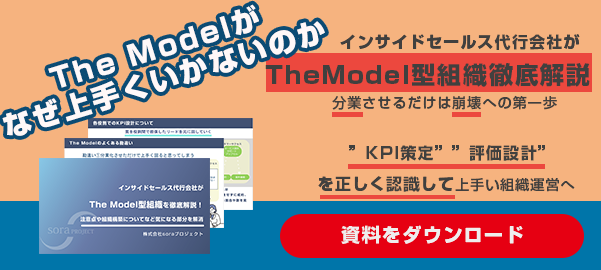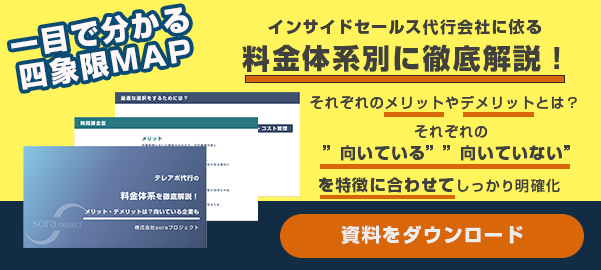目次

- 「インサイドセールスとはよく聞くが、結局何のことを指すのだろうか?」
- 「自社でもインサイドセールスを合理化するにはどうすればよいだろうか?」
- 「他社はどのように実施ているのか?」
上記のように考えている担当者は多いのではないでしょうか?インサイドセールスは営業活動の根幹となる部分であり、正しく意味を理解しておく必要があります。
またどのようにすれば合理的に運用できるのか、他社成功事例からも謙虚に学ぶ必要があるでしょう。そこで本記事では以下について解説します。
- インサイドセールスの定義
- 高度なインサイドセールスを実施している成功事例5選
- 事例から学ぶインサイドセールスのメリットや導入方法
本記事を読めばインサイドセールスを成功させる道筋が見えてくるはずです。
インサイドセールス=オフィス内での営業活動

インサイドセールスとは、電話やメール、Web会議システムなどを用いて、オフィス内部から営業活動を行う方法のことを意味します。たとえばテレアポやリストマーケティングなどがここに分類されます。
具体的には、事前に収集しておいた顧客リストを用いて営業電話を行い、情報収集をはじめた顧客をフォローアップします。
担当者は顧客へ有益な情報提供やヒアリングを継続的に実施。製品やサービスへの興味関心を惹きつけるわけです。いわゆるリードナーチャリングは、このアクションをしまします。
インサイドセールスの担当者が育成した見込み顧客のリストは、実際に訪問する営業担当者へ引き渡されます。つまりインサイドセールスからフィールドセールスへ移管されるわけです。
実際の商談において成約へ結び付けるには、インサイドセールスの時点でどれだけ受注確度を高められるかがポイント。つまりどれだけよいパスをフィールドセールスに出せるかが重要になります。
フィールドセールスとの違い
インサイドセールスと似た言葉で、「フィールドセールス」という営業手法があります。フィールドセールスとはいわば、従来からある訪問型営業のことです。
フィールドセールスでは、営業マン一人ひとりが取引先の会社へ訪問します。いわゆる外回り営業などが典型的な例だと言えるでしょう。
フィールドセールスには「商品やサービスの複雑な説明をしやすい」「信頼関係を密に構築しやすい」というメリットがあります。しかし訪問できる顧客数には限りがあり、また何も事前情報がなければ効率的に営業活動を展開できません。
そこで重要になるのがインサイドセールスです。ここで十分にリードナーチャリングがなされていれば、スムーズに商談を成功することが可能です。
つまり内勤型のインサイドセールス、外勤型のフィールドセールスの両方を活用しながら、顧客の育成から受注後のフォローまでを一貫しておこなうのが理想系となります。
インサイドセールスにおける成功事例5選

インサイドセールスは一般的な手法であることから、参考にしやすい成功事例が多数出回っています。ここでは特に優先して確認しておきたい事例について解説します。
- 株式会社キャンパス
- 株式会社カオナビ
- トーテックアメニティ株式会社
- 株式会社カケハシ
- 株式会社ナシエルホールディングス
いずれもインサイドセールスで大きな成果を挙げた企業です。それぞれについて詳しく解説するので、参考にしてください。
商談率が37%上昇|株式会社キャンバス
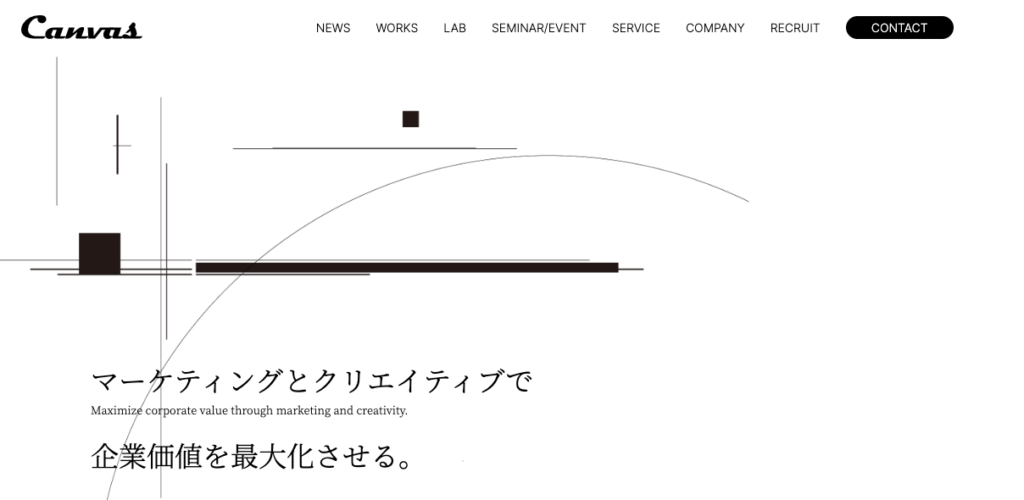
(引用:株式会社キャンバス)
株式会社キャンバスはデジタルマーケティングを中心として、デジタルアートやシステム開発などWEB方面でのクリエイティブを提供する企業です。
同社はインサイドセールスの仕組み自体は有していたものの、営業拠点が多すぎて顧客情報や入電について正確な把握ができずにいました。さらに広告で獲得したリード顧客にもうまくアプローチができず、他社に横取りされる機会損失も。
同社はこの状態を改善するために、顧客管理やリード発掘を適切化するためにインサイドセールスを整備。ツールの導入や人員の増加で体制を整えます。
ここでは特にホットなリード顧客を発掘する姿勢が功を奏しました。インサイドセールスの整備を始めてから、商談が発生する確率が37%もアップ。
リード顧客の発掘は難しい課題ですが、同社の場合は安定して確保できる方法を確立しています。
わずか3名で1ヶ月100件の有力案件創出|株式会社カオナビ

(引用:株式会社カオナビ)
株式会社カオナビは、人事や労務を管理するサポートや支援ツールを取り扱うソフトウェア開発企業です。同社はマーケティング部門とフィールドセールス部門の連携について課題を抱えていました。
せっかく広告を出してもリード獲得につながらない、フィールドセールスにパスを出しても成約しないなど、かなり苦しい状態が続きます。この問題を解決するために、インサイドセールスの改善に着目。
同社の場合は製品・サービスに初期費用0円で導入ハードルが低いことから、「リードナーチャリングに許される期間が極端に短い」という特徴を見つけます。ここで長期スパンでの育成を捨て、できる限り短期間で顧客情報を整理し、早期にインサイドセールスからフィールドセールスへパスが出せるようにしました。
この体制改善が功を奏し、商談のチャンスが拡大。今ではわずか3名のチームで、1ヶ月に有力案件を100件ほど作り出せるようになっています。
重要地区でのリード獲得数が2倍にアップ|トーテックアメニティ株式会社

(引用:トーテックアメニティ株式会社)
トーテックアメニティ株式会社は、ITソリューションやエンジニアリングを手掛ける企業です。
同社はコロナ禍の影響で展示会や合同イベントへの出展取りやめを経験。重要な販路が途絶え、新規顧客の供給不足に苦しむように。自社でのナーチャリングもさほど本格的ではなく、またマーケティング部門不在の状態。
さらにはテレアポも組織的には取り組んでおらず、かなり厳しい状態に立たされていました。
トーテックアメニティは展示会や合同イベントで失った集客ルートの代替え手段を作り出すため、ツールや代行サービスを導入します。そしてコンサルティングのアドバイスを受けて、マーケティングやインサイドセールスなどを部門として分けるようになりました。
さらにテレアポのトークスクリプトや営業記録ツールも用意し、本格的にインサイドセールスを整備します。
この取り組みの成果は、重要視していた地区のリード獲得数が2倍になったり、営業担当者の工数が4割減少したり、コストとリソース両面で現れました。
一時期は販路を失い業績を悪化させた同社ですが、現在では新事業を展開して攻めの経営に転ずるほど状況が開けています。
同業種平均5倍のリード獲得|株式会社カケハシ
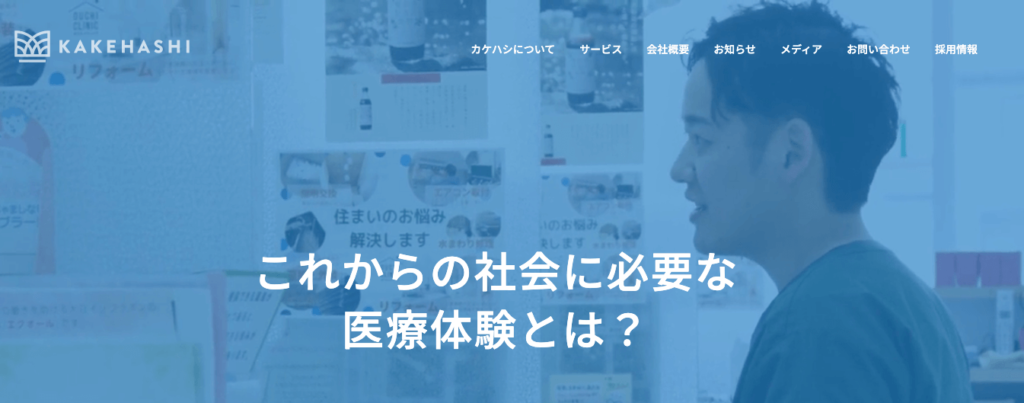
(引用:株式会社カケハシ)
株式会社カケハシは、薬局経営サポートや専用クラウドサービスを提供する企業です。競争激化が著しい薬局業界で、同社の製品とサービスはかなり高い需要を持っていました。
しかし同社のインサイドセールスはさほど安定しておらず、営業が新規開拓できるタイミングがやや限定されていました。また医薬品会社に同行して新規顧客の獲得を狙うも、営業対象のニーズが弱く、思うような結果は出ません。
同社はこの問題を解決するためインサイドセールスの構築を開始し、新しい体制へと移行します。
最初に「テレアポと薬局経営サポートの相性がよい」ということに気づきました。さらにそこからコンサルティングのアドバイスを得るなどして、テレアポ部門を整備。
結果としてアポイント数が同業界の平均値の5倍となり、リード顧客を潤沢に確保できるようになりました。さらにフィールドセールスも常時動かせるようになり、営業経験やノウハウが蓄積。PDCAも高速で周回するほどに状況が改善しています。
株式会社ナシエルホールディングス
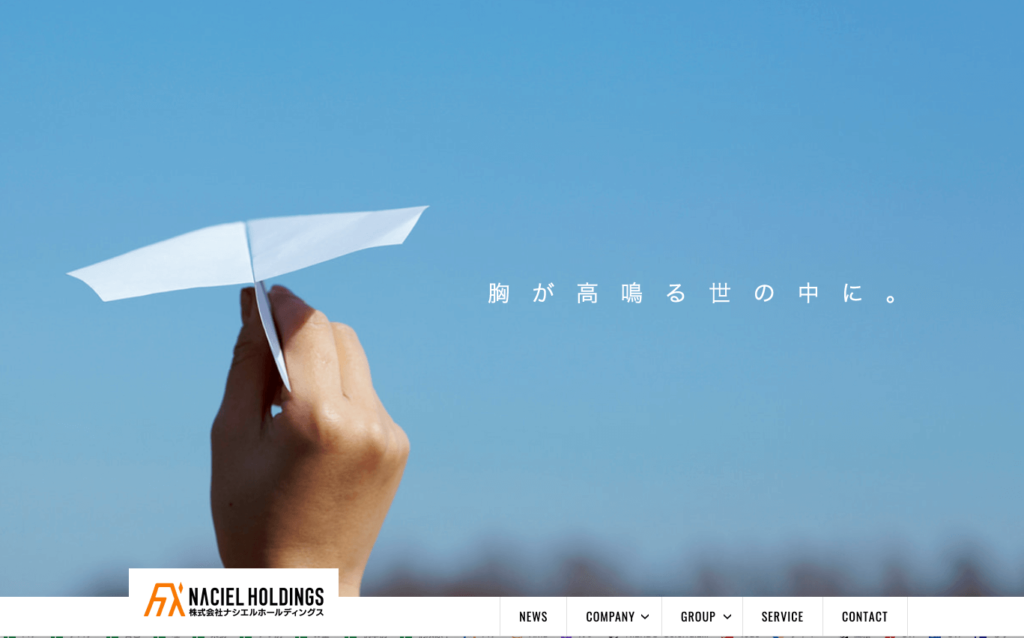
(引用:株式会社ナシエルホールディングス)
株式会社ナシエルホールディングスは、飲食店向けの経営サポートサービスを提供する企業です。
同社は飲食店に対して人材を派遣するため、求職者をリードとして必要としていました。しかし再接触や困難であり、常に新しいリードを確保しなければいけない状態に。また求職者に架電しても就職への意思がさほどでもなく、面談に結びつかないケースが多々ありました。
この問題を解決するために、同社は新しいMAツールを導入。求職者に対してより適切なタイミングで接触できるように状況を整えます。
またメールでの配信も効率化し、あるいはその反応率なども確認して、ダイレクトメールマーケティングも推進。
この結果、同社が架電した場合の求職者との面談の実現率は50%程度まで改善されます。さらにメールを送信し続けることで、転職や就職へのモチベーションを高めるリードなーチャリングも実現。
インサイドセールスで、大きな変化を得られた成功事例です。
インサイドセールスを導入するメリット

上記ではインサイドセールスの改善に取り組み、成功した事例について解説しました。なぜこのように劇的が変化があったかというと、ひとえにインサイドセールスのメリットを適切に得られたからです。
- 顧客へ効率的にアプローチできる
- ホットな状態でフィールドセールスに引き継ぎできる
- 属人化を未然に防げる
これらは成功事例でも関係した、インサイドセールスのメリットです。それぞれについて詳しく解説するので、参考にしてください。
顧客へ効率的にアプローチできる
インサイドセールスはフィールドセールスと違い、リードを獲得するために多くの顧客へアプローチできるのがメリットです。
フィールドセールスでは、およそ4~5件が1日の訪問件数となります。対してインサイドセールスは、1日に60件以上の電話がけができます。
また、受注に至るまでのコミュニケーションにおいても、インサイドセールスが大きな力を発揮するでしょう。インサイドセールスでは、ダイレクトメールやWeb会議システムなど、さまざまなツールを駆使して顧客へアプローチするのが特徴です。
そのため、訪問先へいちいち出向いて説明する必要なく、遠隔からより多くの顧客へ製品やサービスを説明できるのです。市場の変化や競争が激しい昨今では、より効率的にコミュニケーションを行えるインサイドセールスの手法が重要視されています。
ホットな状態でフィールドセールスに引き継ぎできる
ホットな状態でフィールドセールスに引き継ぎできるのも、インサイドセールスが健在であることのメリットです。
先ほども触れたように商談が成功するかどうかは、営業担当者だけではなくインサイドセールスでの準備が十分かどうかにも左右されます。この段階で顧客情報を十分に取得し、リードナーチャリングで興味関心をひきつければ、商談は有利に進むでしょう。
そうすれば営業担当者が現場で大逆転を狙わなくても、安定して成約を実現できるようになります。インサイドセールスで顧客の気持ちを高めて、ホットな状態でフィールドセールスにパスを出しましょう。
属人化を防げる
属人化を防げるのも、フィールドセールスを進めるメリットです。
従来の営業手法では、顧客の受注確度やコミュニケーションの方法など、受注に結び付けるまでのプロセス全般が個々の営業マンにゆだねられていました。インサイドセールスでは属人化を防ぎ、チームで戦略的に関係構築を行えるのがメリットです。
営業プロセスが属人化してしまうと、各営業マンが今までに培ってきたスキルや経験に依存することになります。また本人が離脱する場合は、同時に契約が終了してしまうなどのリスクもあるでしょう。
引き継ぎするとなった場合も問題です。顧客情報は横に流せますが、関係値だけはどうにも承継できません。
しかしインサイドセールスでは、顧客の検討度合いや現状などの情報を、ツールを用いて共有します。「いつ商品の具体的な説明をするのか」「どのタイミングで担当者を訪問させるのか」など、全体でシェアしながら考案することが可能です。
またインサイドセールスが顧客接点を持つことにより一人の営業マンへ依存することがなくなります。つまり属人かではなく属会社かすることで、本人が離脱した場合の痛手をある程度おさえることが可能となるわけです。
インサイドセールスの導入方法

インサイドセールスの導入する場合、以下の3つの方法が活用されます。
- 自社でイチから構築する
- SFAなどのツールを活用する
- 外部委託を利用する
基本は自社で構築することですが、すべてのケースにおいてその余力があるとは限りません。その場合はツールや外部委託が用いられることもあります。それぞれについて詳しく解説するので、参考にしてください。
自社でイチから構築する
インサイドセールスを導入する方法の1つは、自社でイチから導入するやり方です。自社の状況に合わせて柔軟に構築でき、もっとも効率的な体制を形成しやすくなります。一方で導入が困難で、リソースを消費する点には注意しましょう。
自社でイチから構築する際は、Excelやスプレッドシートといった表計算ツールを活用することが一般的です。「見込み顧客の情報」「アプローチの進捗状況」「受注確度」などの項目を設定し、社内で情報を共有していきます。
ただしインサイドセールスは抽象的かつ大きな概念なので、誰も体感したことがない状態からゼロベースで構成するのはかなり難しいミッションです。ある程度経験したことのある社員がいればイチからの導入を、経験がなく初めて導入する場合はほかの方法を検討しましょう。
SFAなどのツールを活用する
SFAやCRMをはじめとしたツールを導入すれば、顧客情報を効率的に管理できるようになります。インサイドセールスにおいて重要な顧客管理を、ツールで一括管理できるのがメリットです。
SFAやCRMを提供しているベンダーの中には、導入後のアフターフォローも行っている会社も存在します。ただツールを導入するだけでなく、実際の現場で成果を出すところまでもサポートしているのが魅力です。
最近では、安価に導入できる「クラウドサービス」も登場してきています。インサイドセールスの本格的な導入を検討している場合は、SFAなどのツール導入も検討してみましょう。
外部委託を利用する
インサイドセールスをはじめて導入する場合に、もっともスムーズなのは外部委託を活用する方法です。イチから構築する方法やツールを導入する方法と比べて、早い段階で成果を上げられます。
外部委託では、インサイドセールスで重要な「商談機会の創出」をワンストップで代行できるのがメリットです。インサイドセールスの専門家が「電話」「メール」「Web会議」などを駆使して、顧客との関係構築を行います。
リードとして育成されたのち、潜在度の高い顧客は、自社のフィールドセールス担当者へ引き渡されます。それにより、無駄な営業の工数を省いて効率的な営業活動を展開できるのがポイントです。
導入時の初期コストや維持費はある程度かかりますが、社内の体制を維持したままインサイドセールスを導入できるのが魅力です。
外部委託は、事業が大きくなってからも、ピンポイントで頼れるサービスでもあります。コストはかかるものの、いつでも自社でインサイドセールスを担保しなければいけない、というわけではありません。
外部委託という選択肢があることを頭の片隅に入れておきましょう。
インサイドセールスを導入して営業改革を行おう

本記事ではインサイドセールスの定義や成功事例について解説しました。
インサイドセールスは内勤型の営業活動を指すものです。オフィスの中から電話やWEBを利用して顧客接点を持ち、間接的にリードなーチャリングを実施します。
そして製品やサービスへの興味を高めた状態で、フィールドセールスでパスするのが基本的な役割です。
非常にシンプルなことに見えますが、これを安定して運用するのは簡単ではありません。しかしフィールドセールスがうまくハマったとき、企業には大きな利益がもたらされます。
成功事例で紹介したように、リード顧客の獲得率が跳ね上がったり、数多くの商談機会を創出できたりします。事例を参考に、自社でもフィールドセールスを導入できないか検討してみましょう。
投稿者プロフィール

-
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様へターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。
最新の投稿
- 2024年4月25日営業代行相見積もりとは?基礎知識とメリット、マナーや注意点を解説
- 2024年4月23日マーケティングTikTok Liteは広告を出稿できる?具体的な方法を詳しく解説
- 2024年4月22日営業代行潜在ニーズとは?引き出す方法やコツ・成功例を解説
- 2024年4月18日営業代行リベートとは?意味や活用シーン・会計処理方法を具体的に解説