目次
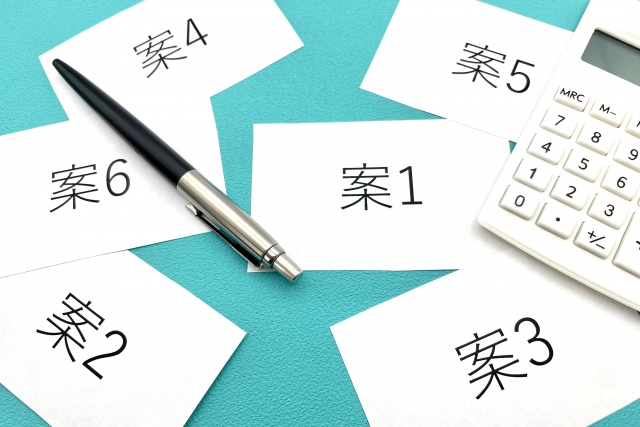
相見積もりは、経費のムダや取引上のトラブルを防止するために欠かせない業務です。
しかし、相見積もりという業務をこなすには、基礎知識やマナーが欠かせません。
本記事では、相見積もりの基礎知識・メリット・マナーを解説します。
注意点やメールの例文もあわせてご覧ください。
【基礎知識】相見積もりとは

相見積もりとは、複数の業者に見積書を依頼し、納期や価格などを比較することです。
見積書を比較すればプランや条件の違いが明らかになり、適正な発注につながります。
また、不自然な価格差が生じている場合に気づくことも可能です。
この章では、相見積もりの基本的な知識を解説します。
1.相見積もりは「あいみつ」とも言われる
多くの企業では、相見積もりはあいみつと略されます。
あいみつを使った例文は以下の3つです。
- リストの業者にあいみつを依頼してください
- 今週中にあいみつをお願いします
- 合計金額が〇円以上はあいみつが必要
あいみつは、企業が活用する商品・サービスを選択する際の大切な業務です。
2.英語での相見積もり表現方法
相見積もりの英語表記は、競争・競合を意味する「Competitive」の後ろに下記の2語を加えて表現できます。
- 入札を意味する「Bid」を使う
- 見積もり・相場を意味する「Quote」を使う
また、具体的な英語の例文は以下のとおりです。
近年では、グローバルな企業も増えているため、英文での使い方も覚えておきましょう。
3.相見積もりと合い見積もりは同義
相見積もりと合い見積もりは、いずれも正しい表記です。
ただし、社内での表記は統一しましょう。
なぜなら、表記がまちまちでは混乱を招く可能性があるためです。
相見積もりと合い見積もりの表記は、企業によって異なりますが、一般的には「相見積もり」が使用されています。
4.相見積もりは失礼ではない
相見積もりは、ほとんどの業界で実施されており、失礼な行為ではありません。
相見積もりによって複数の業者が失注することを申し訳なく思い、見積もり依頼を躊躇してしまう人もいるのではないでしょうか。
しかし、相見積もりの必要性は業者も理解しており、商品・サービスの改善に活用されます。
相見積もりは、業者と取り引きする上でメリットがあるために生じた手法です。
相見積もりのメリットは、次章で解説します。
相見積もりの3つのメリットとは

相見積もりは、業者との取り引きで生じる可能性のあるさまざまなリスクを回避するための手法です。
どのようなリスクを回避できるのかは、相見積もりのメリットを知ることで判明します。
本章では、相見積もりの3つのメリットを解説します。
メリット1.適正価格を把握
相見積もりによって複数業者を比較する中で、市場価格を把握できます。
市場価格は購入する規模や時期によって異なるため、明確な値はありません。
相見積もりを実施して、はじめて平均値を割り出せます。
メリット2.相手の対応を確認
相見積もりは、やりとりから相手業者との相性を確認できるのもメリットです。
相見積もりのやりとりからは、対応力の高さやレスポンスの早さがわかります。
商品・サービス購入後のことも考慮すると、業者との相性を確認するのは大切です。
メリット3.適正な取引を実施
相見積もりは、企業の透明・公正な取り引きを実現するために必須です。
その理由は、主に下記の2つです。
- 購入担当者による特定業者との不公正な取り引きを防止できる
- 悪徳業者との取り引きを防止できる
相見積もりで業者を比較するときは、正当性を証明できる明確な要素を探し、コーポレートガバナンスを守りましょう。
相見積もりの5つのマナーとは

相見積もりは失礼な行為ではないものの、互いに不快な思いをしないためのマナーも存在します。
業者との関係性を壊さないために、マナーを守って相見積もりを実施してください。
本章では、相見積もりの5つのマナーを解説します。
マナー1.相見積もりと伝える
相手の業者の勘違いを防ぐために、事前に相見積もりであることを伝えてください。
相見積もりと伝えなかった場合は、業者が受注確定と考えて準備を進めてしまうリスクが想定されます。
相手業者との関係保持や発注トラブル防止のためにも、相見積もりと事前に伝えることが重要です。
マナー2.同条件で相見積もり
異なる条件での相見積もりでは比較・検討ができません。
なぜなら、条件に応じて見積書の内容が変わり、公平な比較ができないためです。
依頼中に条件や発注数が変更になった場合は、相見積もりを依頼したすべての業者に、変更内容を同時に伝えます。
マナー3.見積書の納期を伝達
相見積もりの際は、比較・検討する予定日から逆算して見積書の納期を策定・伝達します。
納期を設定することで、公平性のある比較・検討ができます。
見積書の納期の目安は最低でも一週間です。
見積書の納期を一週間以内に設定したケースでは、業者の対応が間に合わない可能性があります。
マナー4.見積書の内容を漏らさない
見積書には、製品の金額や手数料など、社外秘となるレベルの情報が記載されています。
そのため、外部に見積書の内容を漏らす行為はやめましょう。
例えば、見積書を競合他社に提示しての値引き交渉はもってのほかです。
見積書の情報漏えいは、作成を依頼した業者からの信頼を損ねてしまいます。
マナー5.見積書の期限内に回答
相見積もりで獲得した見積書には、ほとんどの場合に回答期限が設けられています。
相見積もりの回答は、受注業者・失注業者の双方に対して実施します。
失注業者への連絡は気が引けますが、連絡をしなければマナー違反になると覚えておきましょう。
相見積もりで確認すべき3つのポイントとは

相見積もりは、金額を比較するだけが目的ではありません。
適正な取り引きにするためには、さまざまな視点からの確認が必要です。
本章では、相見積もりで確認すべき3つのポイントを解説します。
ポイント1.見積書の内訳
見積書の内訳を確認する作業からは、商品・サービスにともなって発生する手数料・工賃・資材費・配送料などの詳細を把握できます。
内訳を詳細に比較できる見積書は、検討時の判断材料のひとつです。
見積書には、信頼を獲得する目的で重要な項目や価格比重の高いものを中心に記載するのが一般的です。
内訳を提示しない業者は可能な限り避けるか、内訳の提示を求めると確実と言えます。
ポイント2.提示された条件
見積書に記載される条件は、主に下記の5つです。
- 納期
- 納品場所
- 支払い期日
- 支払い方法
- 特記事項
上記の条件を確認し、自社が想定している条件と合致するかを確認します。
同時に、自社の決裁者にも条件を再度確認し、問題がないかをすり合わせると安心です。
ポイント3.有効期限
一般的に、見積書の有効期限は1~3か月ほどです。
見積書に有効期限を設ける理由は、市場価格の変動にともない、見積書を作成した時点での受注が困難になる場合があるため。
見積書の有効期限が切れたときは、作成を再度依頼しましょう。
相見積もりのメール例文【コピペ可能】

相見積もりの依頼メールを、業者ごとに作成するのは大きな労力です。
またお断りする際は、相手に気を使った文面を考えなければなりません。
本章では、依頼時とお断り時のメール例文を掲載します。
コピペして、テンプレートとしてご活用ください。
1.相見積もり依頼時のメール例文
まずは相見積もりを依頼するときのメール例文です。
購入する製品によっては、見積書の作成に詳細な仕様を掲載した資料が必要となる場合もあります。
その場合は、依頼文に資料を添付することを書き加えて、資料とともに送付してください。
2.購入を断るときのメール例文
続いて、お断りのメール例文です。
件名:見積書の検討結果について
本文:
株式会社〇〇(依頼先の企業名)
〇〇部 〇〇様(送付先の部署・担当者名)
平素よりお世話になっております。
このたびは、〇〇(製品名)の見積書を作成・提出いただきありがとうございました。
弊社にて検討を進めた結果、条件が合わなかったため、他社からの購入が決定致しました。
またの機会にお声がけすることもあるかと存じますので、今後共よろしくお願いいたします。
〇〇株式会社 〇〇部 担当:〇〇
上記の例文では、他社から購入する理由をあいまいな表現にしていますが、実際に使用するときは具体的な理由にしてください。
金額・納期など、具体的に提示することで、相手の改善点のヒントにつながります。
相見積もりを取得するステップ
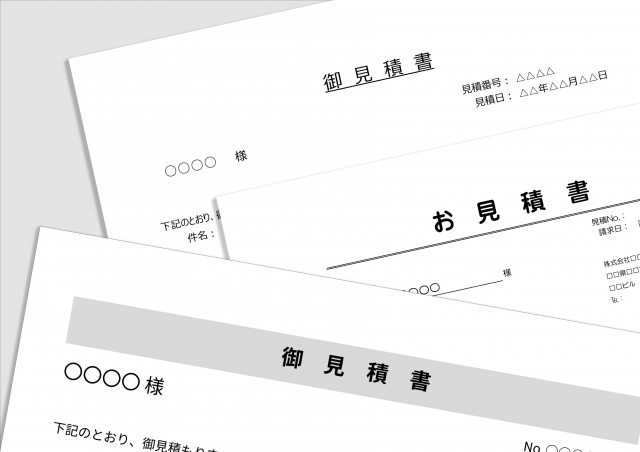
相見積もりを取得するまでのステップは、以下の4工程です。
- 条件の策定:発注目的・発注条件・業者の選定基準を策定。発注条件は見積書依頼時に提示するため、可能な限り詳細に記載する。
- 相見積もり依頼業者のリストアップ:3~4社をリストアップする。業者数が多い場合、絞り込みに時間がかかるため。候補は自社との取引先から探しはじめ、不足したときはインターネットや調査会社を活用する。
- 相見積もりを実施:リストアップした業者に対して相見積もりを依頼する。
- 業者の比較・検討と契約:金額・条件をもとに比較・検討を進めて契約する。
比較・検討を進める段階では、条件や金額の交渉が必要な場面もあります。
条件や金額を交渉を実施するときは、相手の事情をくみ取り、互いに納得できるように話しあうことが大切です。
テレアポで相見積もり業務を効率化できる

相見積もりは適正かつ公正な取り引きには欠かせない存在です。
しかし、相見積もりは複数業者とのやり取りがあり、担当者の業務負担が大きくなりがちです。
当メディアを運営する株式会社soraプロジェクトでは、テレアポ代行サービスを提供しております。
当社のテレアポは電話の取り次ぎだけでなく、継続的な新規顧客開拓にも対応。
確度の高い新規顧客開拓でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

-
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様へターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。
最新の投稿
- 2024年5月2日マーケティングプロダクトアウトとは?メリット・デメリット、成功事例まで徹底解説
- 2024年4月30日マーケティングタッチポイントとは?強化によって得られる効果・方法を詳しく解説
- 2024年4月29日営業代行営業でクロージングを成功させるためには?成約率を高めるテクニックやスキル・ポイントを解説
- 2024年4月25日営業代行相見積もりとは?基礎知識とメリット、マナーや注意点を解説
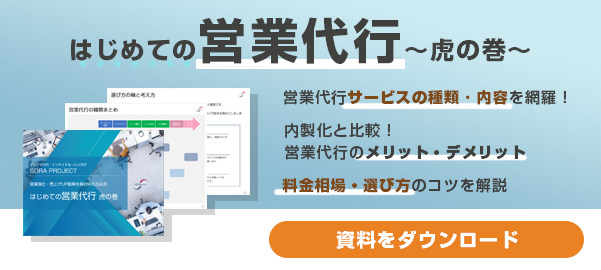










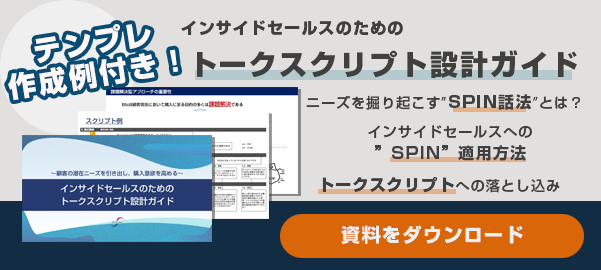
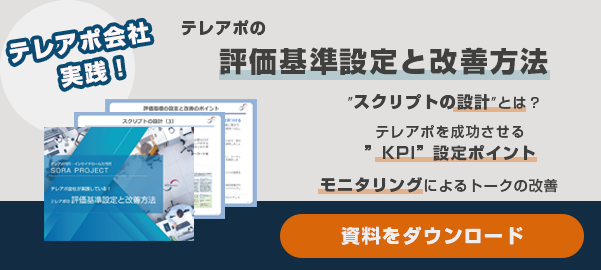
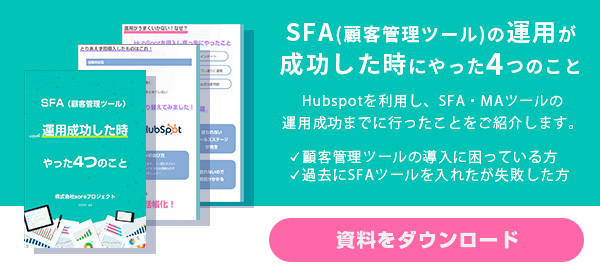
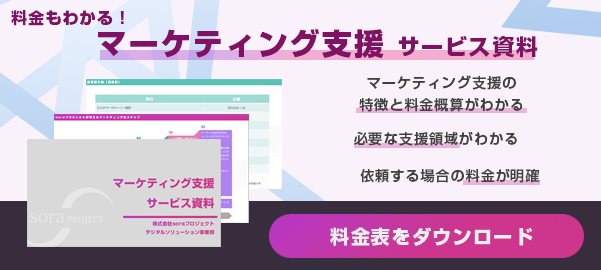
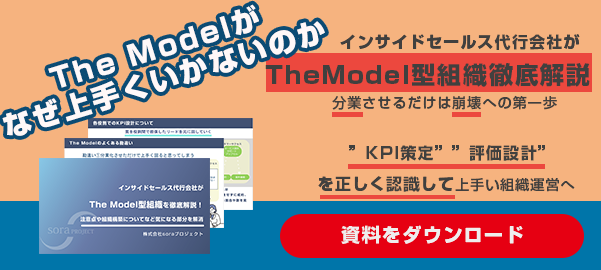
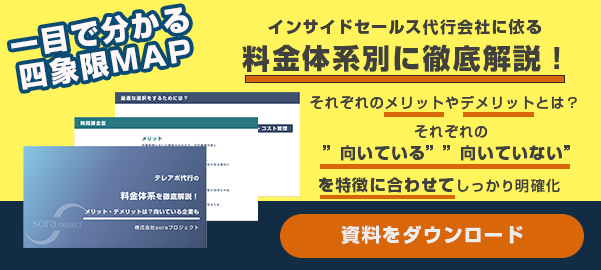
件名:見積書作成依頼について(自社名)
本文:
株式会社〇〇(依頼先の企業名)
〇〇部 〇〇様(送付先の部署・担当者名)
平素よりお世話になっております。
このたび、当社では「〇〇(製品名)」の購入を検討しております。
つきましては、下記の内容について製品代金と必要経費を含めた見積書を依頼したく連絡致しました。
商品名:〇〇
個数:〇〇個
納入場所:弊社〇〇支点
見積書提出期限:〇年〇月〇日
本案件は複数の同業他社に対して見積もりを依頼しております。
発注先については、提出頂いた見積書をもとに検討を進めて参ります。
なお、選定結果は〇月〇日までの連絡を予定しております。
お手数をおかけしますが、対応のほどよろしくお願いいたします。
〇〇株式会社 〇〇部 担当:〇〇