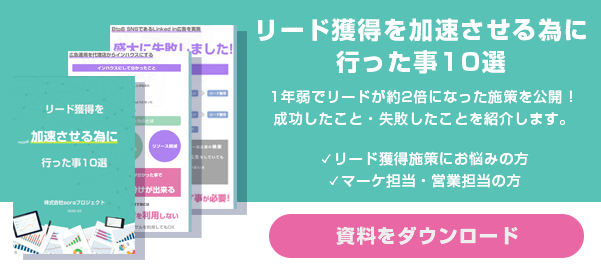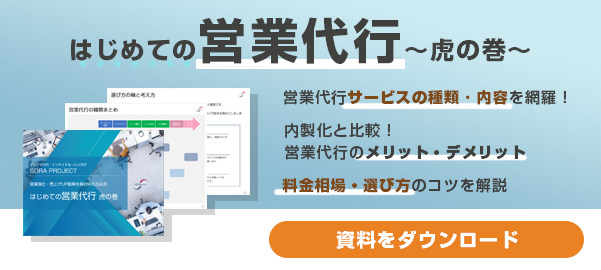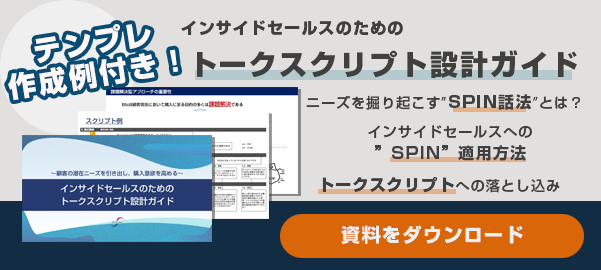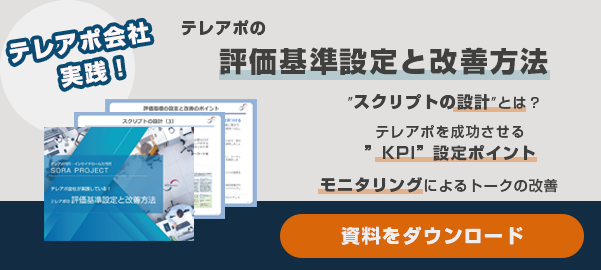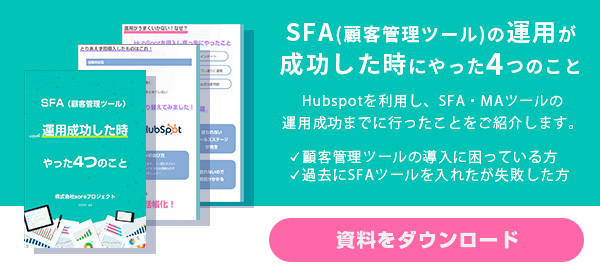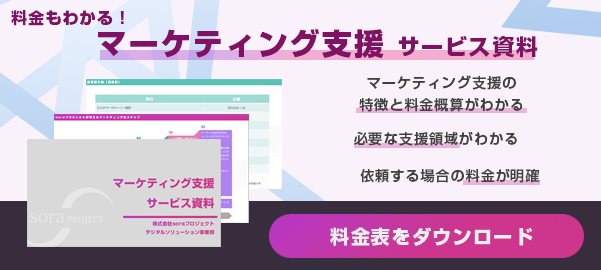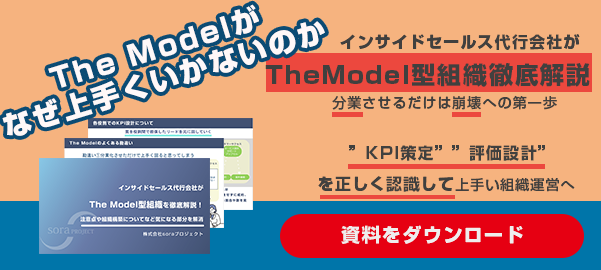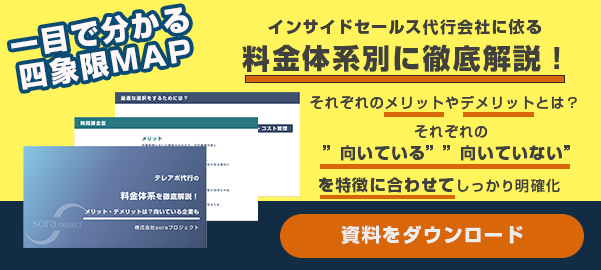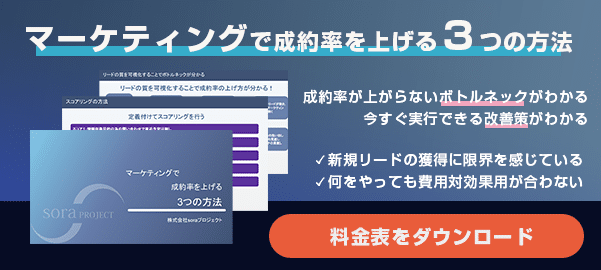目次
プロダクトレッドグロース「Product-Led Growth」は、直訳すると「製品主導の成長」という意味を持ちます。
最近、よく聞くようになりましたが「どのような意味か分からない」「従来のセールスと何が違うのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、プロダクトレッドグロースの意味はもちろん、メリットや自社製品に適しているかの判断基準も解説していきます。
なお、株式会社soraプロジェクトでは「料金もわかる!マーケティング支援サービス資料」を無料で配布しています。
プロダクトレッドグロース(PLG)とは
プロダクトレッドグロースとは、マーケティングや営業までを社員がすることなく、プロダクト自体がそれらを担うビジネスモデルです。
主にSaaSビジネスと相性の良い手法です。
例えばZoomやSlackは無料でも使えるツールです。
無料で提供することで多くの顧客が製品やサービスを試し、「有料版を使いたい」と思えば購入に至ります。
この過程に売る側の人間は入ってきません。
プロダクト自体に魅力や使いやすさがあれば社員が動く必要はなく、ユーザーが自ら購入してくれます。
※SaaS:インターネットを通じて提供されるサービスやソフトウェア
プロダクトレッドグロースとセールスレッドグロースとの違い
セールスレッドグロース(SLG)とは、営業担当者が製品やサービスを販売する従来型のビジネスモデルです。
マーケティングで顧客を獲得し、営業担当がアプローチして顧客が興味を持てば、そこで購入に至ります。
プロダクトレッドグロースとセールスレッドグロースの違いは、下の図を見ると分かりやすいでしょう。
プロダクトレッドグロースは、プロダクト自体がその価値や魅力を伝えられます。
上の図を見ると分かるように、プロダクトレッドグロースには「サービスの閲覧や情報提供」の工程がありません。
セールスレッドグロースよりも早い段階でプロダクトを使用してもらえます。
そのため、購入までの時間も短くなる傾向にあります。
プロダクトレッドグロースのメリット
プロダクトレッドグロースのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは一つひとつを詳しく解説していきます。
早い段階での見込み顧客(リード)獲得
プロダクトレッドグロースは、営業担当が製品を売り込む工程がないため、早い段階で見込み顧客を獲得できます。
プロダクトレッドグロースにはフリーミアムやフリートライアルが設けられているケースが多く、「まずは試してみる」ことが可能です。
- フリーミアム:期限なしでプロダクトを部分的に無料で利用でき、高度なサービスは有料
- フリートライアル:一定の期間だけプロダクトを部分的・完全に無料で利用できる
顧客獲得コスト(CAC)の低減
プロダクトレッドグロースは営業やマーケティングに人員を割く必要がないため、高額な顧客獲得コストがかかってしまう心配がありません。
また、プロダクト自身が営業やマーケティングを行ってくれるため、少ない人員でも機能します。
そのため、社員一人当たりの売上も上がることでしょう。
結果的に、費用や人員を他の製品の開発やプロダクトの改善に回せます。
セールスサイクルの短期化
プロダクトレッドグロースでは、顧客自身がサービスに触れることで機能や使い方を理解していきます。
使っているうちにプロダクトの魅力を感じられれば、その顧客はいずれ有料ユーザーへ切り替わるでしょう。
プロダクトに魅力を感じるのが早いほど有料ユーザーへと切り替わる時間も短くなり、セールスサイクルの短期化が可能です。
導入後のトラブル防止
従来のセールスレッドグロースでは、製品やサービス導入の決定は上層部の社員でした。
しかし、実際に製品やサービスを利用するのは現場の社員であるため、導入後にトラブルが起きてしまうケースもあります。
プロダクトレッドグロースであれば、実際に使う社員が無料で試せます。
そのため、有料に切り替える前に使用感や自社に適切なサービスなのかの判断が可能です。
顧客の利用に合わせた提案ができる
プロダクトレッドグロースなら、顧客の利用に合わせた提案が可能です。
提案は、プロダクト内で行えます。
「〇〇機能の利用方法はこちら」といったメッセージを表示すれば、顧客に新しい機能を知ってもらえます。
また「〇〇が期間限定で半額セール」と表示すれば、アップセルやクロスセルの可能性も見込めるでしょう。
- アップセル:製品やサービスをより上位なものに移行してもらうこと
- クロスセル:使用している製品とは別の製品を購入してもらうこと
アップセルやクロスセルについて詳しく知りたい方は、「アップセル・クロスセルとは?意味や違い事例、注意点を解説」の記事を参考にしてみてください。
プロダクトレッドグロースが自社製品に適しているかを判断するフレームワーク
自社製品がプロダクトレッドグロースに適したものなのか分からない方もいるでしょう。
ここでは、プロダクトレッドグロースが自社製品に適しているかを判断するフレームワーク「MOAT」を紹介します。
MOATフレームワークは、以下の4つです。
- Market Strategy(市場戦略)
- Ocean Conditions(オーシャン状況)
- Audience(意思決定者)
- Time-to-value(プロダクト理解までの時間)
ここではそれぞれを詳しく解説していきます。
プロダクトレッドグロース戦略を考えている方は参考にしてみてください。
Market Strategy(市場戦略)
参照:『Ploduct-Led Grows』ウェス・ブッシュ(2020)P50を元に作成
市場戦略については、以下の3つが挙げられます。
- ドミナント型戦略
- 差別化型戦略
- ディスラプティブ戦略
この3つは、競争優位性、プロダクト価格によって上の図のように分かれます。
この中でも、プログラスレッドグロースに適しているのは「ディスプラティブ戦略」と「ドミナント戦略」だとされています。
ドミナント型戦略
ドミナント型戦略とは、「競合他社と比較して価格が安価」「サービスのレベルが高い」場合に最適な戦略を指します。ドミナント型戦略を選ぶ場合は、以下の点を考えてみるといいでしょう。
- フリーミアムモデルを続けられる大きな市場規模があるか
- 競合他社と比較して品質が高いサービスを安価で提供できているか
- ユーザーはプロダクトを、人手を介さず自分だけで体験できるか
差別化型戦略
差別化型戦略は、「競合他社と比較して価格が高価」「サービスのレベルが高い」場合に適した戦略です。
他社プロダクトのサービスが不十分だと感じている顧客を狙うのに向いています。
差別化型戦略では、ニッチな市場を見つけ出す必要があります。
競合のプロダクトよりも優れた「特定の」機能を取り入れれば、ある企業にはピンポイントに利用してもらえる可能性が高くなるからです。
市場は狭くなりますが丁寧なサポート・高い価格で製品を提供し、差別化が図れます。
このため、差別化型戦略はPLGよりもSLGの方が向いているといえるでしょう。
ディスラプティブ戦略
ディスプラティブ戦略は「競合他社と比較して価格が安価」「サービスのレベルが低い」場合に適した戦略です。
サービスのレベルが低いと聞くと、大丈夫なのかと思う方もいるかもしれません。
これは、CanvaとAdobe Photoshopを例に挙げると分かりやすいのではないでしょうか。
CanvaはAdobe Photoshopと比べると機能面で劣ります。
しかし、デザインを手軽に使いたい初心者にはCanvaが適しています。
「競合プロダクトより安い」「プロダクトの操作が簡単でユーザーが価値を感じやすい」場合はディスプラティブ戦略を選ぶといいでしょう。
Ocean Conditions(オーシャン状況)
オーシャン状況というのは「レッドオーシャン」「ブルーオーシャン」といった市場を指します。
レッドオーシャンは競合が多く存在している市場、ブルーオーシャンは競合がほとんどいない市場です。
ブルーオーシャンはまず、プロダクトを広め、理解してもらわなければいけません。
プロダクトを売る前に、人々に知ってもらうアプローチが必要になるのです。
そのため、ブルーオーシャンではセールスレッドグロースが向いているといえます。
レッドオーシャンでは、人々はすでにプロダクトの活用方法や価値を理解しているため、改めてアプローチする必要がありません。
そのため、レッドオーシャンならプロダクトレッドグロースが向いているといえます。
Audience(意思決定者)
プロダクトレッドグロースにおいての意思決定者は、エンドユーザー(実際に製品を使用する人)を指します。
PLGは「どれだけ早くプロダクトに価値を感じてもらえるか」が大切です。
エンドユーザーが意思決定者(ボトムアップ型)であれば、プロダクトレッドグロース戦略が向いています。
すぐにプロダクトを利用し、気に入れば購入に至ってくれるからです。
しかし、エンドユーザーが意思決定者でない場合(ボトムアップ型)、セールスレッドグロース戦略の方が向いています。
エンドユーザーではなく、企業の上層部にアプローチしなければならないからです。
Time-to-value(プロダクトの価値を感じるまでの時間)
プロダクト理解までの時間が短ければ短いほど、プロダクトレッドグロースが適しているといえます。
プロダクトがすぐに理解できずサポートが必要になる場合、ユーザーは二度とサービスを使うことはないでしょう。
そのため、プロダクトがプロダクトを売る「プロダクトレッドグロース」では、製品理解までの時間が重要です。
「プロダクトはユーザーにとって分かりやすい仕様になっているか」「プロダクトは使いやすいか」を見極め、プロダクトレッドグロース戦略を取るか否かを判断しましょう。
プロダクトレッドグロース戦略に挑戦しよう
プロダクトレッドグロースはサービス自身にマーケティングや営業活動が組み込まれているため、社員の手間を減らし、顧客獲得コスト低減も可能です。
SaaSと相性のいい戦略として広まっており、この戦略を採り入れようとしている企業も増えています。
自社の製品やサービスにプロダクトレッドグロース戦略が活かせるか、この機会にプロダクトの特徴も踏まえて検討してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール

-
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。
最新の投稿
- 2024年5月9日マーケティングTikTok広告のログイン方法は?広告の種類・メリットを解説
- 2024年4月2日営業代行ファクトファインディングとは|意味や目的、やり方や例文まで徹底解説
- 2023年12月18日テレアポ時価総額1000億円以上の企業は?各種ランキングとリストを紹介
- 2023年12月7日営業代行アカウントエグゼクティブとは?仕事内容・必要なスキルを詳しく解説