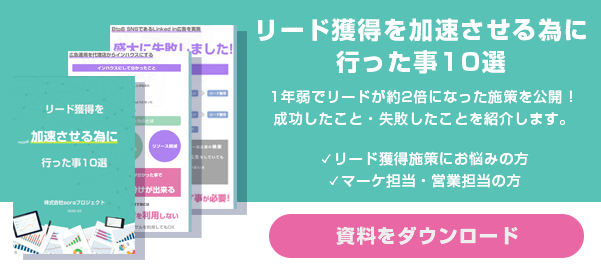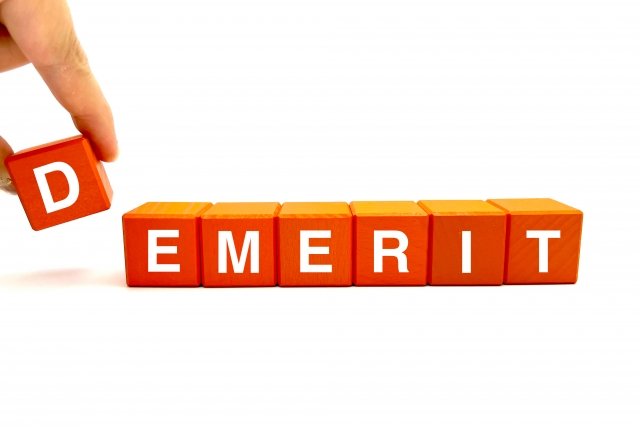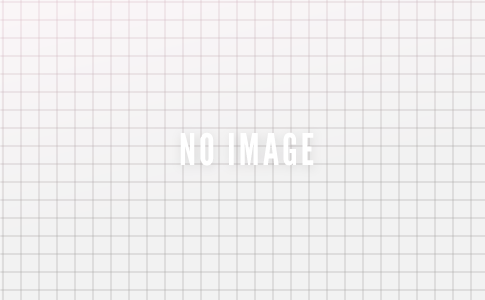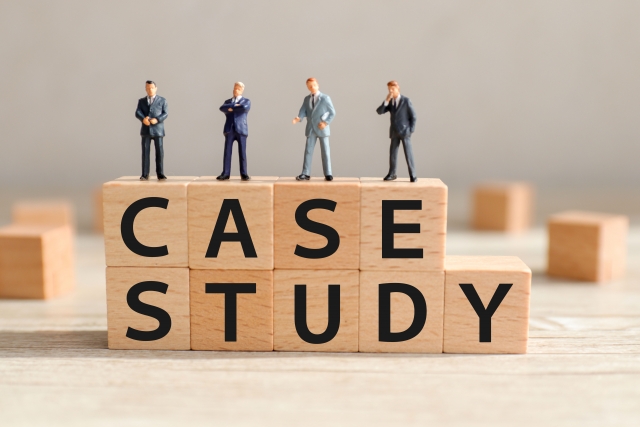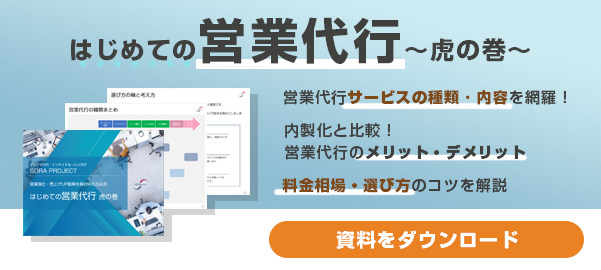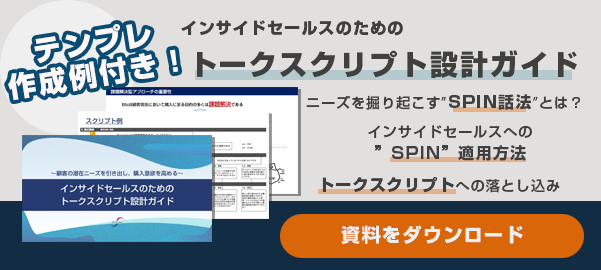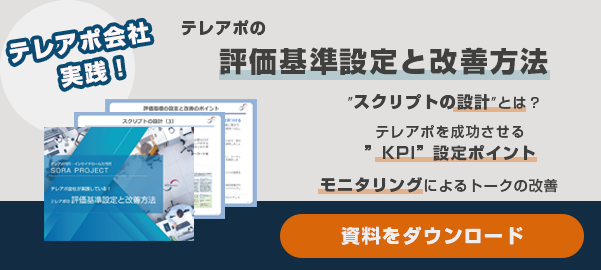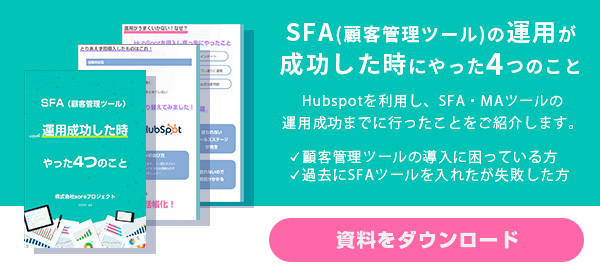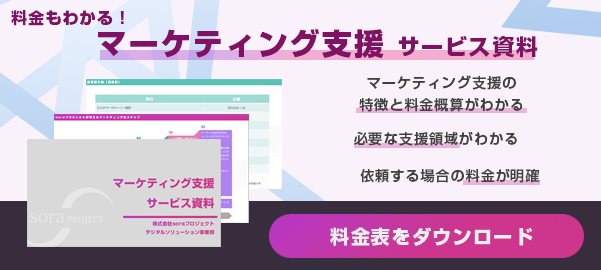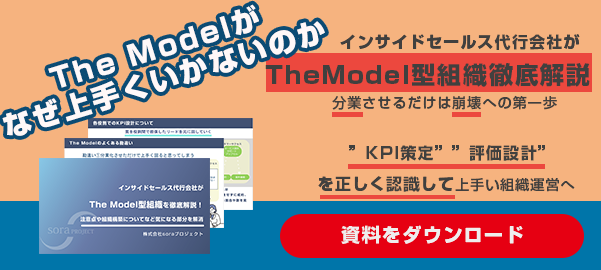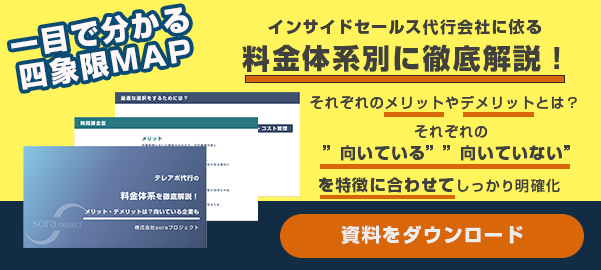目次
- インサイドセールスとはどういったものか?
- 基本的な体制や、アウトバウンド・テレアポとの違いは何か?
- インサイドセールスの体制を整えるメリットは何か?
上記のような疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか?
インサイドセールスは、一度機能し始めれば企業に対して恩恵をもたらします。一方で体制を整えるハードルは高く、導入を諦めるケースも少なくありません。
本記事では以下の点を解説します。
- インサイドセールスの基本的な体制や注目される理由
- 体制を整えるメリットやデメリット
本記事を読めばインサイドセールスの基本的な部分はほぼ理解できます。ぜひご参考にしてください。
なお、株式会社soraプロジェクトが提供するインサイドセールス代行の「料金とサービス資料」を無料で配布していますので併せてチェックしてみてください。
インサイドセールスとは?基本的な体制
インサイドセールスとは、架電やメールを使って顧客に間接的に営業したり、マーケティング戦略を実行したりする部署です。わかりやすく言えば、内勤営業に該当します。
従来の営業活動といえば、商談に出向いたり、飛び込み営業をしたり、足を使うのが基本でした。もちろん、これはフィールドセールスとして現在も存在します。
しかし近年ではインサイド・フィールドでの分業が進み、双方をバランスよく強化するのが常識となりつつあります。
基本的な体制
インサイドセールスの基本的な体制は、以下のように解説できます。
- マーケティング部門
- Web担当部門
- テレアポ部門
上記3部門がインサイドセールスの基本形です。マーケティング部門が顧客や市場を分析し、Web担当部門がコンテンツを公開します。そしてコンテンツを通して回収した顧客リストに対して、テレアポ部門が架電して商談を作り出します。
近年では通話ではなく、Web会議を使って交渉するケースも増えてきました。
アウトバウンドやテレアポなどの部門との違い
インサイドセールスは他の部門と混同されがちです。
特にアウトバウンドとの違いがわからない人は多いでしょう。アウトバウンドとは、企業から顧客へ積極的にアプローチする営業手法を指します。つまり、インサイドセールスとはまったく異なる概念だとわかります。
テレアポとは、インサイドセールスの中に含まれる部門・役割のひとつです。リストや顧客情報に基づいて架電し、アップセルやクロスセルを提供したり、商談のアポイントを設定したりします。インサイドセールスの一角がテレアポであると理解しておきましょう。
インサイドセールスが注目される理由
インサイドセールスが注目される理由は、大きく分けてふたつ挙げられます。
まず、消費者の情報収集活動がWeb上に移行した点です。近年ではインターネットやスマートフォンの普及で、店舗ではなくWebサイトで情報を集めるようになりました。
その後必要があれば、資料を請求したり、問い合わせたりするのが現在の主流です。
インサイドセールスでは、上記のようなアクションからメールアドレスや電話番号を獲得し、架電したり、DMを送信したりします。つまりWeb上での情報提供とアプローチが実施できるため、インサイドセールスが注目されるようになりました。
また営業コストをおさえられる効果があるのも関係しています。元来では直接会いに行く営業が定着していましたが、交通費や人件費が企業の負担となりました。
しかしインサイドセールスを実施することで出費をおさえられる、という意味合いで、注目を集めるに至ります。
インサイドセールスの体制を整える基本的なステップ
インサイドセールスの体制を整えるには、基本的に以下のステップで進めることとなります。
- インサイドセールスにより達成したい目的を明らかにする
- 必要なツールを導入する
- 達成したい目的に必要な人員と費用を計算する
- 実際に運用を開始する
というように、インサイドセールスは目的を明らかにし、それに必要なヒト・モノを用意することで実施できます。
ただし実際に行動するのは簡単ではありません。会社全体で準備し、協議を繰り返しながら長期的なプランで進める必要があります。
インサイドセールスの体制を整えるメリット
インサイドセールスの体制が整えられた場合、以下のようなメリットが得られます。
- リード獲得にかかる時間を短縮できる
- 商談がスムーズになり受注の確率が高まる
- 営業部門の負担を軽減できる
- 営業部門の属人化を予防できる
あくまでも一部ですが、上記だけでも企業にとっては重要な効果をもたらすものです。それぞれ詳しく解説するので、ご参考にしてください。
リード獲得にかかる時間を短縮できる
インサイドセールスを導入する最大のメリットとして、「リード獲得にかかる時間を短縮できる」という点が挙げられます。
仮にインサイドセールスを実施しないなら、各社に足を運び、1件ずつ接触しなければいけません。すると、1日に2、3件程度しか商談をこなせないわけです。
一方でインサイドセールスであれば、リード獲得にかかる時間が短縮できます。例えばテレアポで1件30分かけるなら、8時間労働だとしても16件はアプローチができるわけです。
すなわち、リード獲得にかかる時間を短縮し、製品やサービスをより多くの顧客に届けられるようになります。
商談がスムーズになり受注の確率が高まる
インサイドセールスを実施すれば、商談がスムーズになります。
なぜなら、当日までにインサイドセールスで見込み顧客としてナーチャリングするからです。
例えば顧客の課題を聞き出したり、あるいは製品やサービスに関してある程度の解説をしたりすることが可能。
つまりホットな状態でフィールドセールスにパス、つまり営業マンに引き渡します。すると営業マンは、かなり有利な状態で商談へ臨めるようになります。
だとすれば、通常の商談と比較して受注できる確率は高くなるといえるでしょう。
営業部門の負担を軽減できる
インサイドセールスを実施すれば、営業部門の負担を軽減できます。なぜなら、営業がやっていた付随業務を吸収できるからです。
インサイドセールスが充実していない場合、例えばテレアポなどの業務も、フィールドセールスにいる営業担当者が実施しなければいけません。また新規開拓も足を運び、飛び込み営業せざるを得ないといった状況にもなり得ます。
これでは商談に集中できず、営業成績にも悪影響が及ぶでしょう。
しかしインサイドセールスがテレアポを実施したり、ナーチャリングしたりすれば、営業部門の負担を軽減し、結果として商談の結果も好ましいものになります。
営業部門の属人化を予防できる
営業部門の属人化を予防できるのも、インサイドセールスを実施するメリットのひとつです。従来の営業では、取引先に対して一人の営業担当者を派遣し、関係構築するのが基本でした。
となると、一人の営業担当者に属人化するのは当然です。本人が離脱すると、その企業との関係も途切れてしまうかもしれません。
しかしインサイドセールスが実施できていれば、ツールなどを通して企業との状況や関係性に関して、自社内で共有できます。したがって営業担当者だけで情報が独占されず、属人化を避けられるわけです。
インサイドセールスのデメリット
インサイドセールスにはさまざまな利点がありますが、一方で以下のようなデメリットもあります。
- 情報共有のシステムを組まなければいけない
- 複雑な交渉には向いていない
- 人材の確保が必要
特に3点は、インサイドセールスを導入した際、新しい課題となりがちです。それぞれ詳しく解説するのでご参考にしてください。
情報共有のシステムを組まなければいけない
インサイドセールスを実施するうえで、まず情報共有のシステムを用意するコストとリソースが必要になります。基本的にはSFA・CRMツールを導入することとなるでしょう。
そうすると、ツールの利用料金が必要なうえ、導入や運用の手間もかかります。状況によっては使用方法などをレクチャーする研修なども、開催しなければいけません。
のちほど解説する人員の確保を含め、情報共有の仕組みづくりは大きなハードルとなるでしょう。
複雑な交渉には向いていない
インサイドセールスは、複雑な交渉には向いていません。やはりテレアポやWeb会議ツールではコミュニケーションが取りづらく、込み入った話はしづらい部分があります。
重要性が高く、また複雑な話し合いになる場合は、フィールドセールスによる商談を実施しなければまとめるのはむずかしいでしょう。したがって、交渉の難易度に応じてインサイドとフィールドどちらで実施するのか振り分けを検討するなどの工夫も必要です。
人材の確保が必要
インサイドセールスを実施するには、当然ながら人材の確保が必要です。
例えばマーケティングやテレアポ、そしてWebと部門を分けるなら、それぞれにスペシャリストを見つける必要があります。
しかし、各部門で十分な戦力となる人材を集めるのは簡単なことではありません。場合によっては、採用活動に相当な注力が必要になる可能性もあります。
多くの人材を要するのは、インサイドセールスにおける大きなデメリットだといえるでしょう
インサイドセールスに関するQ&A
本記事では、インサイドセールスの体制やメリットについて解説しました。最後に、よくある質問に対してQ&Aの形式で回答します。
- インサイドセールスを学べる書籍はないか?
- どういった人材がインサイドセールスに向いているか?
- インサイドセールス立ち上げの失敗事例とは?
それぞれ詳しく解説するのでご参考にしてください。
インサイドセールスを学べる書籍はないか?
インサイドセールスを学べる書籍はかなり限定されています。現状で以下2冊が候補となるでしょう。
インサイドセールス 訪問に頼らず、売上を伸ばす営業組織の強化ガイド/茂野明彦
インサイドセールス 究極の営業術 最小の労力で、ズバ抜けて成果を出す営業組織に変わる
上記2冊はAmazonやKindleでの販売実績が豊富で、好意的なレビューも目立ちます。ただしインサイドセールスを立ち上げるのではなく、すでに部門は存在していることを前提にしている内容が多い点に注意してください。
どういった人材がインサイドセールスに向いているか?
インサイドセールスに向いている人材として、以下が挙げられます。
- リスト作成や架電など、多様なタスクに対応できる
- 営業の心理を理解し、商談がやりやすいようにサポートできる
- 架電およびビデオチャット上でもコミュニケーションを取れる
- マーケティングに関する知識がある
インサイドセールスに求められる素養は多種多様ですが、最低限でも上記4点は必要です。特にマルチタスクになりやすいため、事務的な処理能力があればテンポよく業務を捌けるでしょう。
インサイドセールス立ち上げの失敗事例とは?
インサイドセールス立ち上げの失敗事例として、以下が挙げられます。
- そもそもツールや人員を揃えられない
- インサイドセールスが先行して、フィールドセールスの商談が間に合っていない
- 営業先の情報や知識が共有されていない
- マーケティングに対して、改善点などを共有できていない
- インサイドセールスが、営業担当者の求める情報を提供できていない
インサイドセールスは、多様なポジションと多くの人数が関係する複雑なセクションであり、失敗事例も多々考えられます。上記のようなありがちなパターンにはまらないように注意して、体制を考えなければいけません。
インサイドセールスの体制づくりを成功させよう

本記事では、インサイドセールスの体制について解説しました。最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- インサイドーセールスの基本的な体制は、マーケティング・Web・テレアポの3部門があれば成立する
- インサイドセールスが注目されるのは顧客の情報収集行動がWeb上に移行しつつあるから
- インサイドセールスの体制が整えば、リード獲得にかかる時間を短縮できたり、受注確率を高めたりする
- 属人化を予防したり、履歴管理できたりするのもポイント
インサイドセールスの体制が整った場合のメリットは重要です。営業成績、つまり自社の売上も大きく成長するでしょう。
一方で多種多様な人材を適切に配置しなければいけない側面があり、導入ハードルは高めです。
自社で一丸となり、導入へ向けて長期的に取り組む必要があるでしょう。「soraプロジェクト」は、インサイドセールスに属するテレアポ・営業・マーケティングに関して代行サービスを提供しています。14年以上の運営歴があり、経験に裏打ちされたノウハウで、顧客のセールス活動を力強くサポート。
セールスでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
投稿者プロフィール

-
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。
最新の投稿
- 2024年4月2日営業代行ファクトファインディングとは|意味や目的、やり方や例文まで徹底解説
- 2023年12月18日テレアポ時価総額1000億円以上の企業は?各種ランキングとリストを紹介
- 2023年12月7日営業代行アカウントエグゼクティブとは?仕事内容・必要なスキルを詳しく解説
- 2023年12月4日営業代行パートナーセールスとは?3つのメリットや戦略ステップを徹底解説