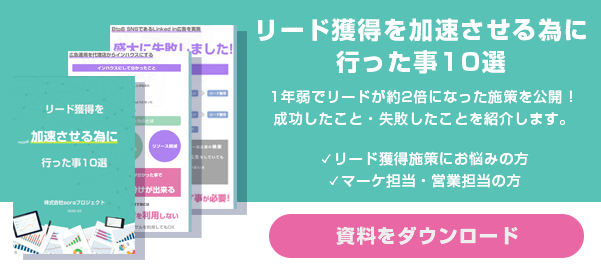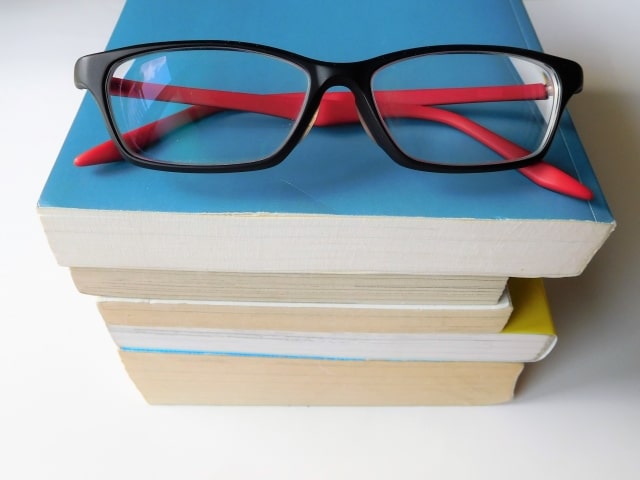目次

インサイドセールスを立ち上げたいと思っているものの、どのように行えばいいのか悩んでいる企業担当者の方は多いでしょう。
インサイドセールスを導入する企業は多くありますが、立ち上げ時に注意することを把握しておかなければ、せっかくの施策も失敗になりかねません。
本記事では、インサイドセールスの概要から立ち上げる際の5つのポイントについて詳しく解説します。
本記事を読めば、インサイドセールス立ち上げに失敗するリスクを下げられるはずです。
ぜひ最後まで読んで、インサイドセールス立ち上げにお役立てください。
インサイドセールス立ち上げ前に概要を確認

本章では、インサイドセールス立ち上げ前に概要や従来の営業とは違う点についてご紹介します。
インサイドセールス立ち上げ前に、まずは関係者間で共通認識を持って施策に取り組むことで、失敗するリスクを減らせる可能性が高くなります。
一方で、「他社もやっているから」と安易な理由でインサイドセールスを立ち上げても、上手くは行かないでしょう。
まずは本章で、インサイドセールスの概要を把握し、立ち上げ前の準備をしていきましょう。
インサイドセールスとは?
インサイドセールスとは、B to Bにおける営業手法のひとつで顧客を直接訪問せず、電話やメールを使って見込み客に接触を図り案件化をめざす営業活動を指します。
セミナーや展示会、広告、Web施策などのマーケティング活動により収集した見込み客(リード)のうち購入意欲の高い層(MQL: Marketing Qualified Lead)に対してコンタクトするのが一般的とされています。
インサイドセールスの活動範囲は商談案件化するまでで、その後はアウトサイドセールス(フィールドセールスともいう)に引き渡すという企業が多くを占めますが、商材によってはすべての営業活動をインサイドセールスのみで行い、成約まで担当する場合もあります。
インサイドセールスと従来の営業手法の違い
インサイドセールスはテクノロジーの力で営業活動を効率化した、従来にはない新しい形態の営業手法です。
諸説ありますが、インサイドセールスは、アメリカのテレマーケティングが起源といわれています。国土の広いアメリカで営業活動を行うには、直接訪問は移動コストが高くなるため電話による顧客アプローチが盛んでした。
インターネットの普及に伴い、メールを使った資料の送付が一般的になり、顧客管理システムやWeb広告などの発展によりセールスの仕組みが大きく変わりました。
最新のインサイドセールスはこれらの仕組みを組み合わせ、顧客の課題やニーズをデータから把握し、適切なソリューションを顧客に提示することで高い案件化率を実現しています。
ツールやシステムの発展と同時にインサイドセールスも普及し、立ち上げを検討する企業が増えています。
インサイドセールスと営業アシスタントとの違い
営業アシスタントは、営業を補佐する職種です。従来の外勤型営業(アウトサイドセールス/フィールドセールス)は移動に多くの時間を費やすため、営業アシスタントが不在の間の顧客の電話対応やスケジュール管理、見積書・契約書の作成などを行います。
現在ではモバイル端末や業務システムのクラウド化により、社内にいるのと遜色のない業務ができるようになっています。そのため営業アシスタント業務の総量が減少しており、営業部門内にインサイドセールスチームとして再編成することがよくあります。ただし、業務内容が異なるため、インサイドセールスの設置部門については他の組織との連携や顧客との関係性なども考慮する必要があります。
商材の特性や社風を考慮し、適切にインサイドセールスチームを活動させることが大切です。
インサイドセールス立ち上げ時のポイント5つ

インサイドセールス立ち上げ時のポイントについて5つ紹介します。
立ち上げ時のポイントを把握することで、活動を行う際にスムーズに取り組むことが可能になります。
本章でインサイドセールス立ち上げ時のポイントについて、それぞれチェックしながら読み進めてみましょう。
ポイント1.インサイドセールス立ち上げ時にKPIを設定する
インサイドセールスの業務は見込み客(リード)にメールや電話で接触を図り、商談案件を創出することです。マネージャはチームメンバーがこのミッションを円滑に実行する環境を整え、目標を達成するための指標(KPI)を設定します。
まず、インサイドセールスの活動に必要な環境とは、見込み客(リード)の個人情報(会社名・部署名・電話番号・メールアドレス)と、行動履歴、インサイドセールスでの活動履歴を入力・管理できるツールです。一般的には顧客管理システム(CRM/SFA)を使います。
CRM/SFAがすでに導入されている場合でもシステムにデータが正しく入力されていないと、電話が通じない、メールが届かない、名前や行動データが間違っていて逆に不審感を抱かせてしまったなどの問題が発生しますので、立ち上げ時にはクリーンなデータを整えることを心がけてください。
ポイント2.インサイドセールス立ち上げ時には社内への認知と部門内調整をする
環境整備と同時並行になるのが、社内への認知です。
インサイドセールスはマーケティング部門から見込み客(リード)情報を受け取り、案件化したらアウトサイドセールスに引き渡すという中継ぎの役目を担います。そのため、マネージャーはインサイドセールスの守備範囲を明確にし、マーケティング部門と営業部門との連携をしっかり行えるように社内での認知と関連部門とのコミュニケーションを良好に保つ必要があります。
部門間の連携がうまくいくことによって、例えば、マーケティング部から渡されたリードが商材のターゲットと少しずれていて案件化率が低いような場合、インサイドセールスで得られた情報をマーケティング部門に適切にフィードバックすることで、ターゲットのズレが修正され案件化率の向上を期待できます。
ポイント3.インサイドセールス立ち上げ時には目標設定をする
インサイドセールスはマーケティングで獲得した見込み客数(リード)に対して案件を発掘することがミッションなので、母数は[見込み客数]。目標とする指標は[案件数]になります。目標数を達成するための鍵になる指標(KPI)は[案件化率]です。
営業活動がインサイドセールスのみの場合は受注数が目標になり案件数および案件化率は目標を達成するための鍵指標(KPI)になります。
営業全体のプロセスは、マーケティングでの見込み客獲得から、インサイドセールスで案件化、アウトサイドセールスでの受注、さらには再受注まで続いています。インサイドセールスが案件化率だけを上げることに盲目になると次のステップの受注率が下がるといったように全体が機能しなくなるので、適正な目標数を設定して確実に次のステップに渡していくことが大切です。
ポイント4.インサイドセールス立ち上げ時には入力負担の少ないツールを選定する

切れ目のない営業プロセスを引き継ぎ、マーケティング、インサイドセールス、アウトサイドセールス間の分業をスムーズにするには、情報の受け渡しが重要です。
SFA/CRMを活用すると、顧客情報を管理し、案件ごとの活動内容を入力できます。ただし、データ入力が不十分だと、ツールの価値が半減します。チームメンバーにデータ入力の重要性を周知するとともに、入力負担を軽くする工夫が必要です。
しかし、1日に複数の顧客と何本ものメールや電話対応を行い、その記録をすべて入力する作業は大変です。入力項目が多すぎたり入力画面が使いにくかったりすると、入力が手薄になり歯抜けデータが多くなることが多々あります。
ツール選定時にはメンバーの入力負担を軽くしつつ、重要な項目は必ず入力させる工夫が必要です。
ポイント5.インサイドセールス立ち上げ時にはマーケティング部と営業部との連携とる

繰り返しになりますが、インサイドセールスはマーケティング部門と営業部門の間に位置し、各組織が分業できるよう求められます。
そのために、前のステップの指標が次の指標の母数になるような考え方をセールスフォース・ドットコムが提唱しています。具体的にはマーケティング部の指標の見込客数が次ステップのインサイドセールスでの案件数を算出するための母数になり、さらにその案件数がアウトサイドセールスでの受注数を算出するための母数になるといった具合です。(下図参照)。
出典:「営業効率を最大化する「The Model」(ザ・モデル)の概念と実践」より
マーケティング部の指標の見込客数が次ステップのインサイドセールスでの案件数を算出し、その案件数がアウトサイドセールスでの受注数を算出することで、営業プロセスが掛け算でつながっていることがわかります。
数値目標とコミュニケーションが連携することで営業実績を向上させることができます。インサイドセールス立ち上げ時には指標として検討しましょう。
インサイドセールス立ち上げは適切な方法で慎重に進めよう

本記事では、インサイドセールスの概要から立ち上げ時のポイントを5つ紹介しました。
インサイドセールスは従来の営業手法とは大きく異なり、安易な理由で導入すると失敗になりかねません。
しかしインサイドセールスは比較的新しい営業手法でもあるため、立ち上げに苦労する企業も多いはずです。
多くの場合社内にノウハウがないほか、インサイドセールスに詳しい人材がいないこともあり、立ち上げをスムーズに行うことが難しいケースもあるでしょう。
立ち上げには少なからず労力や時間がかかるものです。
自社で立ち上げが難しい場合は、インサイドセールスを外注してみてはどうでしょうか。
株式会社soraプロジェクトでは、インサイドセールスの代行サービスを行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

-
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様に
ターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。
最新の投稿
- 2024年5月9日マーケティングTikTok広告のログイン方法は?広告の種類・メリットを解説
- 2024年4月2日営業代行ファクトファインディングとは|意味や目的、やり方や例文まで徹底解説
- 2023年12月18日テレアポ時価総額1000億円以上の企業は?各種ランキングとリストを紹介
- 2023年12月7日営業代行アカウントエグゼクティブとは?仕事内容・必要なスキルを詳しく解説