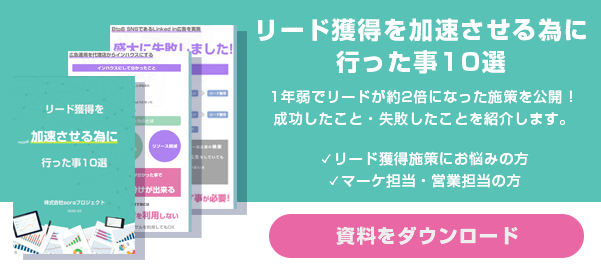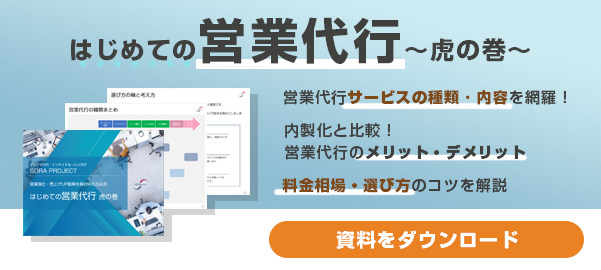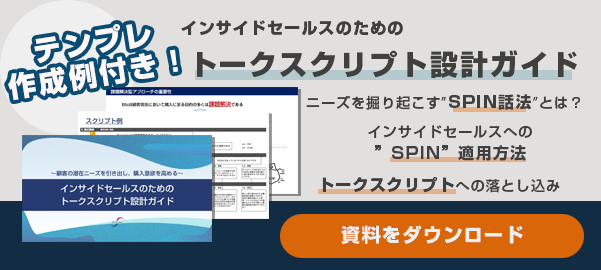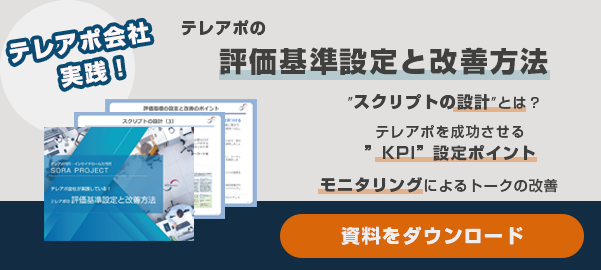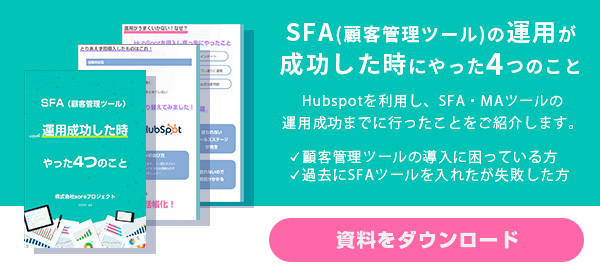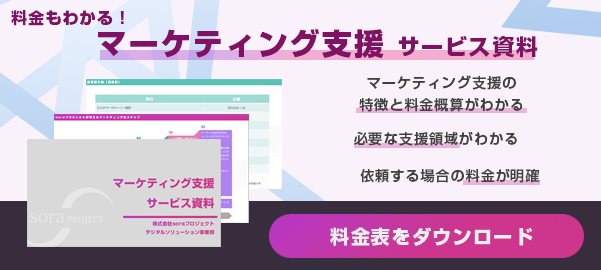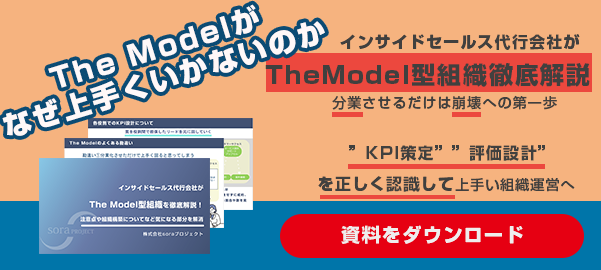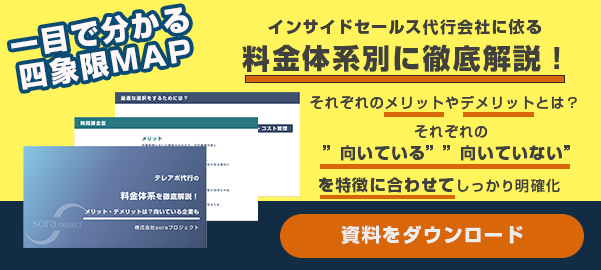目次

あなたは、注意を怠ると電話営業が違法になるケースがあるのをご存知でしょうか?
実は、無意識に違法行為を行っている企業が意外と多いのも事実です。
電話営業は新規顧客を獲得し、ビジネスを成長させるためにとても重要な役割を担っており、多くの企業が電話営業を行っています。
しかし、電話営業は誤った方法で行ってしまうと、違法行為になってしまい、結果として、業務停止・禁止などの行政処分や刑事罰などが発生してしまう可能性があります。
そこで今回は、電話営業で違法になってしまう例を5つご紹介し、詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、自社の電話営業が違法行為になることを防ぐことができ、安心して継続することができるようになるでしょう。
それでは早速、解説していきます。
【注意】電話営業は特定商取引法の適用があります

訪問販売や通信販売のように事業者側から営業をかける行為については特定商取引法が適用されます。
そして、電話営業にも特定商取引法が適用されます。
(特定商取引法では電話営業は「電話勧誘販売」と呼ばれています。)
以下、特定商取引法から引用
「電話勧誘販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、消費者に電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ、その電話において行う勧誘によって、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを「郵便等」により受け、または契約を締結して行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。
難しい言葉が使われていて分かりづらいですが、簡単にまとめると、「電話勧誘販売」とは、事業者が顧客に電話をかけて商品を売り込み、電話・メール・FAXなどの通信手段で購入を申し込む販売手法です。
電話営業は手軽に始められる営業方法で、新規顧客を獲得できる有効なビジネス戦略です。
消費者にとっても本当に価値あるものを適正な価格で購入できたら良いですが、強引な営業により、納得いかない状態で半ば無理やり契約させられるというケースが多いのも事実です。
そのため、電話営業は特定商取引法の適用があるのです。
電話営業で違法行為をするとどうなる?

では、実際に電話営業で違法行為を行うとどうなるのでしょうか?
電話営業で違法行為を行うと以下の3つの行政規制を受けることになります。
- 業務改善指示(法第22条)
- 業務停止命令(法第23条)
- 業務禁止命令(法第23条の2)
また、行為が悪質かつ深刻だと判断された場合は、罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性もあります。
それでは、詳しく規制について解説していきます。
業務改善指示(法第22条)
業務改善指示とは、利用者を保護する上で問題があると判断された場合に行われる行政処分です。
処分された企業は業務改善計画を提出し、進捗状況を報告しなければなりません。
さらに、自主的な改善がみられないケースや、悪質と判断された場合、より重い業務停止命令や業務禁止命令などの処分がされる可能性があります。
業務停止命令(法第23条)
業務停止命令とは、業務改善指示で指摘された問題点の改善に専念させる必要がある場合や、明らかに悪質だと判断が認められた場合に業務停止命令の処分がなされます。
さらに、法令違反の内容があまりにも深刻で悪質だと判断され、業務の継続が不当であると判断された場合は、業務禁止命令などのより重い処分が適用される場合もあります。
業務禁止命令(法第23条の2)
業務禁止命令とは、業務停止命令よりも重い処罰であり、法令違反があまりに深刻で悪質であると判断された場合に行われる行政処分です。
業務禁止命令の内容としては、会社の役員や業務を統括する人が指示を出したり、停止を命じられた範囲の業務を新たに開始することを禁じる処分を受けます。
その他罰則
あまりに悪質だと判断された場合、上記の行政処分の他に、刑罰を下される可能性もあります。
個人には3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金刑が定められています。
以上が、電話営業で違法行為を行った際の処分や罰則になります。
続いて、違法行為になってしまう5つの行為について解説していきます。
売り上げを伸ばすために行った電話営業が原因で、行政処分や刑罰を受けてしまうと、企業の信頼を落としてしまい、本末転倒です。
しかし、冒頭でもお話ししましたが、知らず知らずの内に違法行為を行っている企業が多いのも事実です。
以下で解説する5つのポイントは押さえておくようにしましょう。
電話営業でこれをすると違法です【違法行為5例】

それでは、電話営業で違法行為になる5例を解説していきます。
もし、知らずに電話営業をして違法行為に当てはまった場合は、「知らなかった」では済まされないため、きちんと把握しておきましょう。
違法行為になる5例は以下の通りです。
- 違法行為1:事業者名を名乗らない
- 違法行為2:一度断られた相手へ再びの電話勧誘
- 違法行為3:事実と異なる説明を行う
- 違法行為4:威圧的な態度で消費者を脅やかす
- 違法行為5:契約の申込み後に書面を交付しない
それでは、詳しく解説していきます。
違法行為1:事業者名を名乗らない
電話営業における違法行為の1例目は事業者名を名乗らないことです。
電話営業を行う事業者は、勧誘を行う前に必ず、以下の項目を消費者に伝えなければならないとされています。
- 販売業者又は役務提供事業者の氏名や名称
- 電話勧誘を行う者の氏名
- 電話の目的が売買契約または役務提供契約の締結について勧誘する旨
上記を伝え忘れてしまうと、特定商取引法第16条に反することとなります。
電話営業の際は、最低限のマナーでもありますが、自分が何者で、何の勧誘しているかを必ず伝えるようにしましょう。
また、違反を犯さないという意味合いと、相手にこちらの情報を伝えることで安心してもらえるという効果もあります。
違法行為2:一度断られた相手へ再びの電話勧誘
電話営業における違法行為の2例目は、一度断られた相手へ再び電話勧誘してしまうことです。
意外と知られていませんが、電話営業では、一度売買契約をしないと意思表示した相手へさらに勧誘を行ったり、改め再び電話営業することを禁止しています。
相手が拒否しているにも関わらず、強引な勧誘は違法行為に値します。
しつこい電話営業を避け、処罰の対象とならないように回避しましょう。
違法行為3:事実と異なる説明を行う
電話営業における違法行為の3例目は、事実と異なる説明を行うことです。
こちら当然のことですが、電話営業でも事実とは異なる説明を行った場合は、違法行為にあたります。
例えば、「商品・サービスの種類/品質/価格」や「商品・サービスの提供時期/引き渡し時期」などが当てはまります。
もちろん、事業者名や氏名を偽るのも違法です。
当たり前ですが、電話営業の際には事実と異なる説明をすることは避け、違法行為にならないように注意しましょう。
違法行為4:威圧的な態度で消費者を脅やかす
電話営業における違法行為の4例目は、威圧的な態度で消費者を脅かすことです。
威迫や脅迫によって、消費者を脅かす行為が違法とされています。
直接的な恫喝や恐喝はもちろん、間接的・遠回しでも相手に恐怖心を与えるような言動も違法行為です。
例え、強引な方法で無理やり契約させたとしても企業の評判は下がり、結果として売り上げの減少に繋がります。
威圧的な態度や、相手に恐怖心を与えるような言動は避け、違法行為にならないように注意しましょう。
違法行為5:契約の申込み後に書面を交付しない
電話営業における違法行為の5例目は、契約の申し込み後に書面を交付しないことです。
電話営業は成約を頂いて終わりではありません。
成約を頂いたのちに必ず、顧客に対して必要事項を記載した書面を交付する必要があります。
注意点としては、主務省令が定める事項で一切の間違えや漏れなく記載した書面を、顧客へ交付しなければならないことが挙げられます。
また、書面を交付したとしても、記載事項に不備があった場合は、交付していないと見なされてしまうので細心の注意を払いましょう。
追記で注意点ですが、事業者が代金受け取り後に遅滞なく商品の引き渡しが行える場合は、書面の交付は不要です。
自社の電話営業では書面が必要か否かを必ず事前に確認して、違法行為とならないように注意しましょう。
その他で知っておきたい、電話営業における制度

実は、電話営業にもクーリングオフ制度が適用されます。
クーリングオフとは、一定の期間、無条件で申し込みや契約を撤回できる、消費者を守る法制度です。
訪問販売によるクーリングオフ制度が適用されることは広く認知されていますが、「強引な電話営業によって納得いかないまま契約してしまった、」
ということが多いため、電話営業もクーリングオフ制度が適用されています。
そのため、電話営業の際もクーリングオフについてしっかりと説明するようにしましょう。
インサイドセールス代行で営業課題の解決ならこちら
まとめ:電話営業では最低限のルールを守って違法行為を回避しましょう

電話営業では、最低限のルールを守らないと、違法行為になる可能性があります。
違法行為を行った場合は、「業務改善指示・業務停止命令・業務禁止命令」などの行政処分や、個人には3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金刑が下される可能性もあります。
とはいえ、今回ご紹介した電話営業のやり方に注意し、最低限のルールを守れば、違法行為になる可能性は限りなく低いです。
是非、電話営業を効果的に行ってビジネスを成長させましょう。
投稿者プロフィール

-
1985年福岡生まれ
福岡発のインサイドセールス支援会社、soraプロジェクトの代表
スタートアップから外資大手まで700以上の営業支援プロジェクトの実績を持つ。
営業活動でお困りの会社様へターゲットリスト作成から見込み客育成、アポの獲得まで、新規開拓の実行支援が専門分野。
最新の投稿
- 2024年4月25日営業代行相見積もりとは?基礎知識とメリット、マナーや注意点を解説
- 2024年4月23日マーケティングTikTok Liteは広告を出稿できる?具体的な方法を詳しく解説
- 2024年4月22日営業代行潜在ニーズとは?引き出す方法やコツ・成功例を解説
- 2024年4月18日営業代行リベートとは?意味や活用シーン・会計処理方法を具体的に解説